Prologue
どのようにして「JOINTRIBE」という組織が誕生したのか?
創業者 藤井宏次の人生の物語から、JOINTRIBEの存在目的とルーツを紐解きます。
Episode01.起業失敗、世界放浪へ
私は23歳の時に勤めていた商社を辞め、同世代の仲間と共にベンチャー企業を立ち上げました。意気揚々と起業に挑戦し、「成功」を目指したものの、多くの仲間が身体や心を病み、友人同士だった仲間が仲違いするようになってしまい、ビジネスの世界で闇雲に目標達成を追いかけることに意味を出せなくなっていました。2年間で数億の資本金を使い果たし、事業は瞬く間に傾いていきました。事業をたたむことが決まった頃、私はこれから先どうやって何のために生きていくのか、五里霧中・暗中模索の状態にいました。
そんなある日、渋谷で書店にふらりと立ち寄った際、不意にある本が目に留まりました。その本のタイトルは「終わらぬ民族浄化、セルビア・モンテネグロ」というものでした。なんとなくその本を手に取りパラパラとページをめくった私は、背骨に電流が走るような衝撃を受けました。そこにはユーゴスラビア内戦後にセルビア、ボスニアなどの国で連綿と続いている名もない悲劇が描かれていたのです。それらの事件はもはや、テレビや新聞などには取り上げられないようなものでした。
その時私は思いました。「もし今日、この本を手に取らなかったら、自分はこの事実を一生知らなかったのではないか」自分は、自分が生きているこの世界について何も知らない。そのことに気づいたとき、ふと「世界を旅してみたい」と思いました。
当時私は26歳、社会人4年目で、ビジネスパーソンとしてはその後のキャリアを左右する重要な時期に差し掛かっていましたが、悩みぬいた結果、「なんのために働くのか、なんのために生きるのか」という軸がはっきりしないまま、なんとなくビジネスをやり続けることはできないと思い、意を決して世界放浪に出かけることにしました。心の赴くままに世界中を旅し、その中で自分の人生の目的を明確にしよう、そう心に決めたのでした。そのことを決めたとき、文字通り世界が大きく開けていくような言いようのない感覚がありました。
Episode02.レインボーギャザリング
虹の戦士
「地球が病んで 動物たちが姿を消しはじめるとき まさにそのとき みんなを救うために 虹の戦士たちが あらわれる」
これは、ネイティブインディアンの言い伝えとして口伝で語り継がれているもので、「虹の戦士」というタイトルで書籍も出版されています。この言い伝えに基づいて1960年代にアメリカで始まった「レインボーギャザリング」という社会実験との出会いが、その後のJOINTRIBEの誕生や、ティール/ホラクラシーといったテーマにつながっていきます。
シンクロニシティで迷い込んだ異世界
私の旅は神戸から船で上海に渡ることから始まり、シルクロードをバスや電車やヒッチハイクなどの陸路で横断してスペインの西端サンチャゴまで行き、そこからアフリカへ南下し、2年間で世界30か国を周りました。ラオスで臨死体験をしたり、フランスでホームレスをしたり、様々な経験をしましたが、最も強烈な体験がレインボーギャザリングとの出会いでした。
私が初めて「レインボーギャザリング」という言葉を聞いたのは中国で出会った旅人からで、そのあとラオスでも同じ言葉を耳にし、さらにバンコクで出会ったイスラエル人に「レインボーに行くけど、一緒に行かないか」と誘われ、何となくシンクロニシティを感じ、どんなものかも知らずにほいほいついて行ったのでした。バンコクから深夜バスで約10時間、バス停から浜辺を1時間ほど歩いて、朝6時頃、ようやく辿り着いた会場は、「ザ・ビーチ」という映画の舞台のような場所で、満ち潮になると陸の孤島となる辺境でした。
そこには、20人ほどで輪になり瞑想をしている人たちがいたり、波打ち際でクリスタルの球を両手に持って踊っている人がいたり、素っ裸で木に登ってバナナを食べている若者がいたりして、つい数か月前までスーツを着て働いていた私は、どうやら来るところを間違えたと思いました。旅人やアーティストやお坊さん、とにかく多種多様な人々が世界中から集っていて、1か月の開催期間中、浜辺のジャングルを縫うようにキャンプをしていました。


レインボーギャザリングの様子
モノを所有せず、地球をシェアしている
朝日が水平線から顔を出した頃、そんなレインボーギャザリングに何にも知らずにのこのこやってきた私は早速洗礼を受けました。まず最初に目の合った、ものすごく可愛い北欧系の女の子が「Welcome Home!(おかえり)」と言ってハグしてきたのです!一緒にきた他の仲間も同じように「帰郷」を喜ばれていました。「ただいま」を英語で言えなかった私はおろおろしていました。
そして装備ゼロだった私を見た長州力に激似の日本人おじさんが「え、君なんにも持ってないの?僕今日出ていくから、あげるよ」と言って木製のお皿とスプーン、さらにテントまでくれました。最初びっくりしましたが、ここではシェアリングの文化が根付いていて所有という概念が希薄で、どうやら当たり前のことのようでした。
夜になり月が昇る頃、フードサークルという1日2回ある、全員集まって食事の時間になりました。広場には500人ほどの人がいて、大きな二重のサークルを作って地面に座り、ごはんを食べています。隣に同い歳くらいの日本人の女の子が座り、こう言いました。「土の上でごはん食べるっていいよね。星の下でごはん食べるのって美味しいよね」。
いつの間にか忘れていた、そんな当たり前のことを一つ一つ思い出していく時間でした。太陽が沈むと暗く寒く、昇ると明るく温かい。食べ物はお金と交換して得るものではなく、地球が与えてくれて、人が料理をしてくれて、目の前の木のお皿にのっているものでした。
ボスニアでの語らい、あらゆる違いを超えた繋がり
私はレインボーギャザリングに、タイ、ブルガリア、セルビア、ボスニア、イタリア、スペイン、モロッコなど世界各地で延べ6か月ほど滞在したのですが、中でもボスニアでのある夜に見た光景が目に焼き付いています。
森の中、私は焚火を囲んで4人の若い男たちと座っていました。彼らはセルビア、ボスニア、クロアチア、スロヴェニアに国籍を持つ若者でした。彼らは言いました。「僕たちの親同士は殺し合った。でも僕たちは新しい世代だ。僕たちは語り合い、手を繋ごう。」
この言葉を聞いたとき、私は旅に出て良かったと心から思いました。あらゆる違いを超えて繋がっていくこと。JOINTRIBE(JOINT+TRIBE)という社名のルーツは、世界各地でのレインボーギャザリングでの体験にあります。
またもう一つインスピレーションとなったのは、レインボーギャザリングにはリーダーやオーガナイザーが存在せず、数千人数万人が集まる大規模なものでも完全な自主性に委ねられており、にも関わらず、1か月の間に色々な問題が起きつつも自主解決され、なんだかんだ運営されてしまう仕組みでした。
「この運営の在り方を経済社会に持ち込めないだろうか?」と、その時抱いた大きな問いが、その後のティール/ホラクラシーといった組織的なテーマへと繋がっていきます。
Episode03.帰国後、試練の日々
26から28歳の間の2年間の世界放浪は私の人生を決定づけるかけがえのない時間でした。満足いくまで世界を見聞きして周り、自分の信念や価値観についてもかなりクリアーになりましたが、帰国後に長い試練の日々が待っていました。旅の経験や学びをどうやって行動・表現に移していけばいいか分からず人生に立ち往生していたのです。また、2年間の旅によって人生観がガラリと変わってしまい、日本での生活に馴染めず、放浪前に仲良かった仲間とも距離が遠のき、私は典型的な「社会から脱線した人間」となっていました。
バンドでバイオリンを弾く、マクロビオティック(玄米菜食)の普及に努める、シェアハウスを創ろうとしてみる、色々なことに挑戦するのですが、何をやっても中途半端でモノにならず、何一つしっくりこない、そんな日々が1年以上続きました。
そんな中、偶然友人から、ダライ・ラマ法王が来日して講演会をされるとの話を聞き、私は藁をもすがる思いで何かヒントが得られればと、会場である両国国技館へ足を運びました。
私が座ったのは舞台から一番遠い二人掛けの座敷の席で、私はダライ・ラマ法王の話に集中したかったため「頼むから隣に誰も座らないでくれ」と思っていたのですが、開演直前にあくせくと一人の男性が駆けつけてそこに座りました。内心舌打ちしたのを今でも覚えています。しかも、なんと渋滞でダライ・ラマ法王の到着が遅れているとのこと。司会の方が「・・・というわけで、これもご縁ということで、よろしければお隣の方とご談笑されてはいかがでしょうか?」と親切にも促してきたのです。
私は隣に座った男性に対して、「頼むから絶対に話しかけないでくれ」と心の中で鉄のカーテンを引いたのですが、願いかなわず「そんな、談笑と言われても困りますよね!」と彼は朗らかに私に話しかけてきました。そして、「実は僕、劇団で俳優をやってまして、これよかったらどうぞ」と、公演チラシを渡されました。
そのチラシを手に取った私は、そこに初老の白人のポートレート写真と、一行の言葉を目にしました。


2年間の世界放浪
Episode04.師匠レオニード
・アニシモフ
「真実だけが人を治療し、癒すことができる」
それは劇作家、チェーホフの言葉でした。そして写真の方は、ロシア功労芸術家の演出家レオニード・アニシモフという人物でした。なぜかどうしてか、その写真と言葉を見て背骨に電流が走ったように感じ、数か月後、私は劇団の門を叩いていました。
ついに見つけた自分の道
明治維新前夜、山口県の片田舎の萩で、若き日の高杉晋作が松下村塾で初めて吉田松陰に出会ったとき、「自分はこの人についていくしかない」と思ったと司馬遼太郎の歴史小説「世に棲む日日」に書かれていますが、私とレオニード・アニシモフ氏との出会いもそのようなものでした。
参加した演劇ワークショップの初日、トレーニングとして最初に「調律」と呼ばれる俳優の心身をチューニングする瞑想のようなワークをしました。私は世界放浪中にインドで10日間の瞑想合宿に参加したことがあったので、「ああ、それ知ってる」と思い、目を瞑ってその瞑想を始めました。と、次の瞬間、アニシモフ氏がロシア語で何か言葉を発しました。そして通訳の方が言いました。
「こうじさん、インドに行かないでください」
え!この人には私の心の中が透けたように見えているのか!?
その後続いた演劇講義も、目から鱗の驚きの連続でした。アニシモフ氏の演劇芸術に対する思想と哲学の明晰さ、人間に対する深い洞察と愛情、この世界における演劇というものの役割、全てが雲一つない青空のように明快でした。彼は、演劇芸術によって人間の精神や意識は高まることを一点の曇りもなく信じていて、自身の使命を100%理解し、実行していました。
30歳からの役者デビュー
「自分はこの人についていくしかない」私はそう思い、ワークショップの終わる10日目、彼に弟子入りを志願しました。
不思議な感覚なのですが、自分はずっとこの人を探していた、と感じていました。私は演劇だけでなく人生の師と呼べる存在に出会ったのでした。
それから約半年後に弟子入り(劇団入り)を認められ、翌年にはいきなり主役で初舞台を踏むこととなりました。アニシモフ氏に稽古をつけてもらい修行することで、役者としても人間としても急速に成長できる自分を感じていました。その後も2年間で主役を二つ、準主役を一つやらせてもらい、舞台俳優としての滑り出しは身体が一つでは足りないような日々で、私は30歳にしてようやく自分の歩むべき道を見つけたと感じていました。

アニシモフ氏

舞台で演じる私(右)
Episode05.子どもに言われた
ショックな一言
演劇という自分のライフワークに出会い、精進する日々が数年続いていた中、転機が訪れました。
喘息を患った幼い子どもを自然環境の豊かな土地で育てるため、演劇活動を休止し、熊本へ引っ越すことになったのです。
バタバタと引っ越した後、仕事を選んでいる余裕もなく、すぐにできる仕事として完全成果報酬の、一般宅への飛び込み営業の仕事を始めました。しかしこれが本当に大変な仕事で、「こんな時間に来るんじゃねえよ!」と怒鳴られたり、「おめぇ何回目だよ!」と叱られたり(初めてなのに…)、かなりストレスフルな日々を過ごしていました。鏡を見るとげっそりした顔をしていました。
そんなある日、事件が起きました。子どもとお風呂に入っていたときのこと。当時3歳だった子どもが突然、
「こーじー、お仕事つまんないんでしょ?」と言ってきたのです。びっくりした私は半ばごまかすように、「大変なときもあるけど、楽しいときもあるよ」と答えました。しかし彼は曇った顔で「そんなわけないじゃん」と答えました。
この出来事は私にとって頭をガツンと殴られるような、非常にショックなことでした。自分はそういう後ろ姿を見せている、仕事はつまらないものだ、社会は面白くない場所だ、と幼い子どもに刷り込んでしまっているのだと気づかされ、猛省しました。
それから悩みに悩み、そして、どうやってその状況を変えたらよいかは分からないながらも、一つ決意をしました。
「心の底から楽しいと思える仕事を見つけ、それに打ち込み、その仕事で家族を守る」
決意をしてから約1週間後、大きなチャンスが訪れました。世界放浪中にエジプトで出会った友人から突如連絡があり、「うちの会社でコーチング研修をやってもらえないか?」とオファーが来たのです。
さらに、全く同じ日に別の方面から、「演劇を使った幹部研修を企画していて、一度話をしたい」というオファーが来たのです。
研修の仕事などこれまでやったことがなかったのに、同じ日に突如2件、研修の依頼がきたのでした。決意が天に届いた、私はそう思いました。
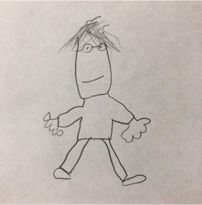
子どもが描いた絵
Episode06.ティール・
ホラクラシー
決意が天に届いたとしか思えないシンクロニシティな出来事をきっかけにコーチングや演劇を使った研修を提供するようになったある日のこと、「ホラクラシー」という見知らぬ言葉を、SNSに大学時代の友人が投稿しているのを見かけました。
初めて見る言葉だったにも関わらず、「どーん!」とまるで飛び出る絵本か3Dメガネをかけて観る映画のように、その言葉が浮き上がって見えたのを覚えています。あまりにも印象的だったために、15年会っていなかった彼に連絡をとり、「ホラクラシーについて聞かせてほしい!」とお願いし、品川のカフェで話をすることになりました。
そこで聞いた新しい組織運営の在り方は、私がレインボーギャザリングで体験したリーダーもマネージャーも存在しないスタイルと類似性のある全く新しいカタチのものでした。強くインスパイアされた私は、勢い勇んでオランダで開催されていた5日間のトレーニングプログラムに参加することにしました。
ホラクラシーの考案者ブライアン・ロバートソンは、かつて見たことがないほどビジョナリーでまた弁が立ち、私にはまるでアルゼンチン代表のメッシかマラドーナのようにファンタジスタな存在に映りました。単純に、強烈にかっこよかったのです。またホラクラシーの哲学や仕組みについても心底インスパイアされた私は、「帰国したらこれを日本に広めよう」と胸を温めました。
帰国後、自分の体験を共有するために「報告会をするので興味ある人は来てください」と、SNSで投げかけたところ、10日後の開催にも関わらずなんと50人ほどの人が集まり、その少し前に書籍「ティール組織」が発売されたこともあり、大きなムーヴメントのうねりを感じました。
その後、フレデリック・ラルー氏が来日した際には3日間に渡って近くで時間を共にさせて頂く中で「組織は生命体であるという世界観」に改めて魅了され、組織進化支援をJOINTRIBEの中心事業としてコミットしていくことになります。

フレデリック・ラルー氏
Epilogue.アートとビジネス
をつなぐ
私はずっと、どこに行っても自分の居場所がない、という気持ちで生きてきました。ビジネスの世界にいても本質的にビジネスには興味がなく、放浪をしている時もいわゆる旅人という人種の人たちとは肌が合わず、劇団に所属していてもずっと演劇をやってきた仲間とはどこか折り合わず、どこに行っても仲間がいないという孤独感と共にありました。
しかし、演劇(アート)とビジネスをつなげた「シアターマインド」というコンテンツを生み出したこと、またティールやホラクラシーと出会ったことにより、自分という人間の役割をやっと見出すことができました。
自分は「狭間」に存在する人間であるということ。自分は右にも左にも属さず、こちら側にもあちら側にもいない。その「狭間」にステイし続け、そこからしか見えない世界をとらえ、そこでしか果たせない役割を果たしていく、そういう人間だということが分かりました。そして世の中には同じような役割を背負った人間がいる、そういう人々がつながり、より大きなミッションを果たしていく未来を意図して、「JOINTRIBE」という法人を生みました。
私の好きな灰谷健二郎さんという作家がこんな詩を書いています。
「自分の知らないところにたくさんの人生がある 自分の人生がかけがえのないものであるように 自分の知らない人生もまたかけがえがない 人を愛するということは 自分の知らない人生を知るということである」
人々が違いや対立を超えて、より大きな目的のもとにつながっていく、そんな未来のために、自分の持ち場で活動を続けていきたいと思います。